子どもが輝く習い事!音楽教室について徹底解説

小学生と幼稚園児を育てるライターのナナコです。
ピアノやバイオリンといった楽器をスラスラと弾きこなせる方は憧れますよね(^ ^)
音楽のスキルを身につけることは人生をより豊かにしてくれるもの。
我が子に音楽の素養を身につけて欲しくて、音楽教室に興味を持つ親御さんは多いのではないでしょうか。
今回の記事では、音楽に関する習い事の種類や教室の選び方、また音楽を習う効果について解説していきたいと思います。
それでは見ていきましょう。
音楽教室の習い事の種類
音楽教室では、楽器や歌など色々な種類を教えてくれますが、今回は次の3種類について説明します。
リトミック
習い事の低年齢化が進んでいる最近では、0歳児でも親子で参加できるリトミックに注目が集まっています。
リトミックはスイスの音楽教育家であるエミール・ジャック=ダルクローズによって開発された音楽教育法です。
音に合わせて体を動かしたり、表現をしたりする教育法で、音感やリズム感などの音楽的感覚を身につけることができます。
大手の音楽教室では、実際にピアノなどの楽器の練習をする前の段階として、リトミックを取り入れているところが多いようです。
- 費用:1回につき500円~3,000円ほど(大手音楽教室での料金の一例)
- 月3回、1回60分のレッスンで入学金5,400円~、月6,000円~(地域によってもだいぶ異なります)
ピアノ
ピアノは昔から人気の高い定番の習い事です。
リズムの取り方や音階などの音楽の基礎が身に付くため、あらゆる楽器の入門としても有効です。
最近では、比較的安価な電子ピアノでも性能が高くなっていることで、必ずしも高額なピアノ(アップライトやグランドピアノ)を用意しなくても始められるのが魅力。
学校の授業でも鍵盤を弾く機会は多く、場合によっては合唱の伴奏などを任されるかもしれませんね。
メジャーな楽器ゆえにピアノ教室は探しやすく、大手の音楽教室や個人教室といった選択肢が多いのもメリットです。
ただし、どのような楽器でもいえることですが、ピアノは基本的に毎日の練習が必要になる習い事。
最初のうちは、ピアノの練習へ向かうよう子どもを促したり、親も一緒にレッスンに付き合ったり負担がかかることは考慮に入れた方がいいでしょう。
- 月謝:6,000円~
- その他の費用:ピアノ本体、楽譜代、検定料、発表会の時にかかる費用など
バイオリン
ピアノに比べると習っている人が少ないバイオリンは、憧れる人も多い楽器の一つではないでしょうか。

成長に合わせて楽器も買い替える必要があることから、お金のかかる習い事というイメージがあるかもしれません。
実際、有名な先生に個人レッスンを受けると謝礼も高額になるようです。
ピアノに比べると教えられる先生も少ないため、月謝も高くなりがちですし、教室の選択肢もやや少なめといえるでしょう。
とはいえ、弦楽器の中では主旋律を奏でることの多いバイオリンは、花形楽器の一つ。
ジュニアオーケストラなどに入って、借りたバイオリンを演奏してみて、続けられそうだと思ったら本格的に購入するという手もあるのではないでしょうか。
- 月謝:グループレッスンなら月8,000円~
個人レッスンなら30分2,500円~(音大教授クラスの先生であれば1時間3万円ほど) - その他の費用:バイオリン、楽譜代、譜面台、発表会の時にかかる費用など
バイオリンは体格に合わせて買い替えが必要となり、4回~5回ほど買い替えが必要な場合もあります
音楽教室の習い事は何歳から?
音楽教室の習い事は何歳から始めた方がいいのでしょうか。
気になるポイントについて解説します。
絶対音感は小さいうちにしか身につかない
絶対音感という言葉を聞いたことはありますか。
絶対音感とは、一つの音だけを聞いて音名を聴き分けられることを指します。
この絶対音感は、6歳半頃までに特別な訓練をすることによって得られるといわれています。
(ただしごくごくまれに特別な訓練を受けなくても絶対音感がある人もいるようです)
絶対音感があることによって、音を聴いて鍵盤を弾くことができるので、演奏などに有利になることが多いといわれています。
しかしながら、有名な作曲家などの音楽家が必ずしも絶対音感があるわけではありません。
何歳であっても訓練次第で身につけられる相対音感があれば、作曲するうえでも問題ないと主張する専門家もいます。
むしろ絶対音感があることによって、音楽を演奏する際に弊害になることすらあるようです。
楽器などの演奏では、演奏効果を高めたり、ハーモニーを作り上げる時にわざと音の高さをほんの少しだけ上下させることがあります。
その際、絶対音感がある人には音がずれて聞こえるため、気持ち悪く感じ、柔軟に対応できなくなることもあるそうです。
「絶対音感さえ習得すれば、必ず立派な音楽家になれる」わけではありませんが、身につけるには適齢期があることを知っておきましょう。
子どもが進む道において絶対音感があった方が有利なのかどうか、音楽の専門の先生に相談するなど、適切に情報収集をすることをオススメします。
やる気になった時が始め時?!
音感教育を始める時期は、脳科学からみても4、5歳頃が適しているといわれています。
生活するのに必要ないと判断された脳細胞は減っていき、残った脳細胞が神経回路を作っていきはじめる時期なので、この頃に五感から入った情報は必要なものと判断され定着していくのです。
このような情報があると親はつい「音楽を始めるなら4、5歳だわ。早くしないと!」と焦ってしまいます。
しかしながら、全く音楽に興味を示していない時に慌ててピアノなどの音楽をやらせるのは必ずしもいいとは限りません。
私は5歳から小学4年までピアノ教室に通っていましたが、小学生低学年から始めた同級生の方が早く上達し、技術的にもすぐに追いつかれてしまったという経験があります。
もちろん友人と私の元々の資質の違いがあったのかもしれませんが、体格や理解力が発達してから始めても遅くはないと思います。
ある程度体格も大きくなり、自分で考えられる年齢から始めた方が結果的に早く上達する場合もあるのではないでしょうか。
興味を持ってその興味が持続して始めた習い事は熱心にやるものです。
友人は、子どもが「ピアノをやりたい」と言い出してからあえてしばらく習わせずに様子を見ていたそうです。
そして1年経ってから本人が「やっぱりやりたい」と強い意志を示したので習わせたところ、自分から熱心に練習をするようになったと言っていました。

音楽というのはレッスンへ行ったときだけにやればいいというわけではなく、自宅での練習の方が大半を占めます。
苦手なところを何度も練習するのですから、決して楽しいことばかりではないのが事実。
途中で面倒くさくなるというのはよくある話です。
熱意があるかどうかは、ツラい練習にも耐えられるかどうかにおいて重要なポイントといえるでしょう。
早く始めた方がいいという一般的な風潮に流されずに、子どもの興味、関心のある時期などに注意を払い、始める機会を検討することが大切ではないでしょうか。
音楽教室に通わせることで期待できる効果は?
音楽教室に通わせることで期待できる効果は一体何なのでしょう。
次から考えられる効果について紹介します。
効果1 地道に努力する力や忍耐力がつく
リトミックでも楽器でも音楽というのは、上達が数字でハッキリと示せるものではありません。
楽器ができる人は他から見るととても魅力的ですが、その華やかさの裏には地道な努力が隠されています。
音楽は日ごろからのたゆまぬ練習がモノをいう世界です。
ピアノにしても弾けない箇所を何度も何度も練習して、思い通りに弾けない部分を少しずつ克服して弾けるようになるのです。
この過程で、地道に努力する力や忍耐力を学びます。
他のスポーツでもいえることですが、練習をしたからといって必ずしも上手くいくものではありません。
時には昨日の方が上手くできたのに・・・とスランプに陥ることもあるでしょう。
それを乗り越えていくことが、努力する姿勢にもつながり、勉強などの困難に遭遇した時もあきらめずに少しずつでも前進する習慣が身に付くようになります。
効果2 気分転換になる
音楽を楽しめると、気分転換になります。
私は中、高、大学時代に吹奏楽部でフルートを吹いていました。
吹奏楽部は地味に見えますが、文科系の中では結構ハードな部活ではないかと思います。
毎日練習をしなければなりませんし、いつも同じ曲を吹いているわけではなくどんどん新しい曲をマスターしていかなければなりません。
体力も使いますし、人数が多いと、仲間ともめ事もあり、なかなか神経を使うものです。
それでも10年近く吹奏楽部にいられたのは、やはり音楽が楽しいからです。
曲を吹いて友人とハーモニーを奏でるというのは、高揚感を感じると同時に癒し効果があります。
ピアノを10年以上習っていた友人は、大人になってからもイヤなことがあったとしても、ピアノを演奏することでリフレッシュができると言っています。
歌が得意であれば、1人でカラオケボックスへ入って歌を歌って発散するのだっていいと思います。
音楽には人の心を癒す力がある、それは間違いなく言えると思います。
音楽教室の選び方
子どもに音楽を習わせたいと思ったら教室を選ぶことになります。
ではどのような点に注意して教室を選んだらいいのでしょうか。
目的をはっきりとさせる
まずは習わせる目的を明確にしましょう。
趣味程度で習わせたいのか、その道のプロとして活躍させることを目標にするのかによって違ってきます。
音楽のプロを目指すのであれば、それ相応の楽器や、指導者など適切な環境を整える必要があります。
音大などの入試では実技が非常に重視されます。
どの指導者に習うかは特に重要ですので、親は情報を集める必要があるでしょう。
口コミなどを確認!気になる教室の発表会を聴きに行くのもおススメ
一方趣味程度で構わないという場合は、どうでしょう。
大手でも個人でも通いやすい教室を探すというのは一つでしょう。
個人教室であれば口コミなどを頼りに探すことが多いので、実際に習っている人や習っていたという人の話を聞いて情報を集めるというのも手です。
気になった教室で発表会をしていれば聞きに行くのもオススメ
生徒の技術がどのようなものかわかりますし、先生が披露する場合は先生の技術を確認することもできます。
体験レッスンなどを受けて先生との相性をチェック
いくつか候補が上がった場合、できれば見学や体験を受けさせてもらって比較することができるといいですね。
先生の人柄や実際に習う環境を確認して、フィーリングが合うかどうかをチェックしてみましょう。
この先生なら子どもを預けられそう、なんとなくウマが合わなそう・・・という直感は意外と当たります。
昔に自分が習ったやり方にとらわれることなく、先生自身も日々学んでいる人はよいですね。
中には親の前ではニコニコしているのに、子どもだけになったら手を叩くなど乱暴な先生もいるようです。
意味もなく暴力的な行為があった時は、子どもの心の傷が深くならないうちに辞めさせるのが一番です。
しかし一般的には子どもにとって合うかどうかがわかるにはそれなりに時間がかかります。
教室には半年から1年ほど通わせて様子を見るのもいいでしょう。
方針が合わなそうだなと何かひっかかることがあれば思い切って別の教室に移ることを検討してもいいかも知れません。
東大生にピアノ経験者が圧倒的に多い理由は○○だった
書籍『頭のいい子が育つ習い事』(東大家庭教師友の会)によると、東大生が幼少期に習っていた習い事で、水泳の次に多いのがピアノといわれています。
東大生にピアノ経験者が多いのは理由があるのでしょうか。
幼い頃ピアノを習っていた東大生に、ピアノを習うことで得られた学力向上効果についてアンケートをとったところ、次のような回答が得られました。
- ピアノは毎日練習しなければならず、勉強習慣につながった
- ピアノで曲を弾くのに苦手な部分を何度も練習するのと勉強で苦手な問題を解けるようにするプロセスが似ている
- ピアノを暗譜することが、勉強で記憶する練習になった
- 発表会で演奏することで、目的に向かって集中して練習することや度胸がついた
などを挙げる学生が多かったようです。
確かにピアノは毎日練習しなければうまくなりません。
毎日決まった時間に練習をするという習慣がそのまま机に向かって学習する習慣の定着につながるのは納得がいきます。
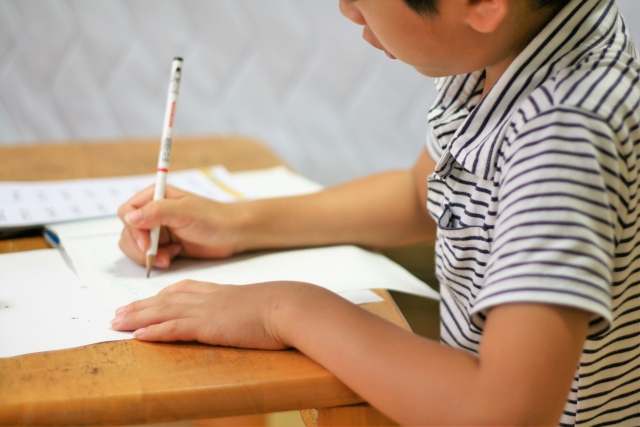
また、曲の中でできない部分を何度も繰り返し練習する作業は、わからない問題を何度も勉強する作業に通じているといえるでしょう。
他には、両指を動かすことによって得られる脳への刺激や、上手く弾けない箇所を上手に演奏するための分析力なども学力向上に一役買っているのかもしれませんね。
大手ピアノ教室のメリットとデメリット
大手のピアノ教室のメリットとデメリットについて紹介します。
■メリット
- 料金やシステムなどが明確でわかりやすい
- ホームページなどで情報収集が容易にできる
- カリキュラムや内容が決まっているので転勤などの理由でスクールを変えても安心感がある
- 受付がいて講師への不満などを伝えやすい
- 駅の近くなど交通の便がいいところが多い
■デメリット
- 比較的料金が高い
- カリキュラムが決まっているため個人の要望が通りにくく柔軟性に欠ける
- 講師を選べない
- 振替ができない教室が多い
- 講師の技量が低いこともある(もちろん技術の高い先生もいます・・・)
個人ピアノ教室のメリットとデメリット
個人ピアノ教室のメリットとデメリットを見ていきましょう。
■メリット
- 大手ピアノ教室よりは安価な教室も見つけられる
- やりたい内容を重視してくれるなど希望に柔軟性をもって対応してくれることが多い
- 指導者が変わらないので、慣れた先生で安心
- 自宅から通いやすい住宅街などで教室を開いていることが多く子ども一人でも通わせられる
■デメリット
- ホームページなどを開設しているところが少なく、情報が少ない
- 仮に先生の指導に嫌な点があってもなかなか本人には言いづらい
- 生徒が少ないと発表会がない場合もある
名の知れた大手のピアノ教室は、長年に渡って研究されてきたノウハウが強みといえます。
一方で、個人の要望に細かく応えてもらうのが難しく、やってもらいたいことがある場合は個人教室の方がいいかもしれません。
先生との相性もありますので、悩んでいる場合は体験レッスンや見学などをして比較をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
楽器などの音楽が上手くなるためには地道な努力が不可欠です。
コツコツと継続する習慣は、勉強だけでなく今後の人生においても生かされることは間違いありません。
なにより音楽を楽しめることは、子どもにとって一生の宝となるはずです。
ぜひ習い事を通じて音楽の魅力に触れさせあげてくださいね(^ ^)
